食品工場の衛生管理、見落としていませんか?工場内の危険リスクと改善のヒント

-
JHTC HACCP上級コーディネーター / MBA
- 鈴木 戒
- コピーしました
- この記事を印刷する
- メールで記事をシェア
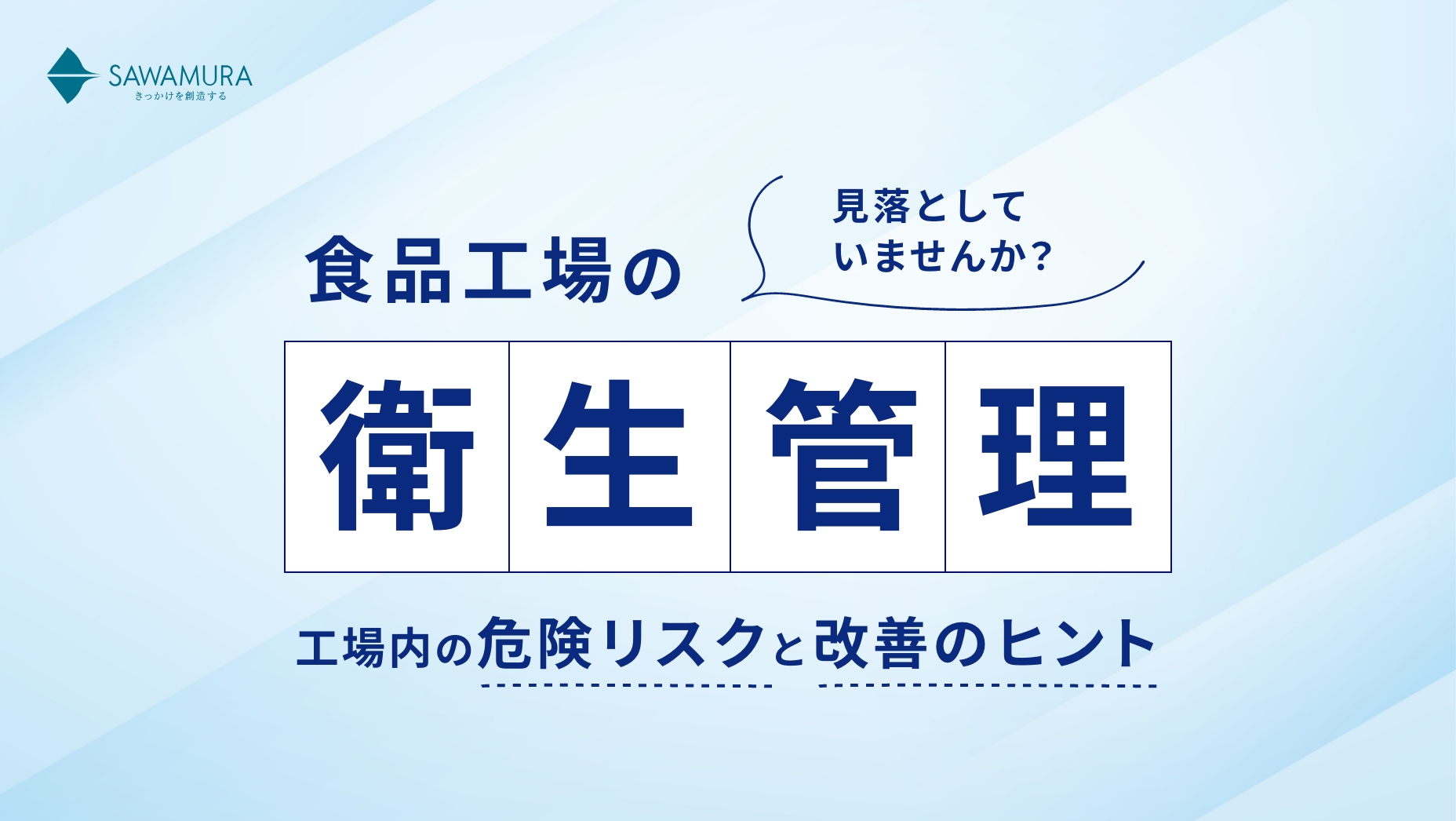
食品を扱う工場では、私たちの口に入る製品を安全に届けるため、衛生管理は何よりも重要です。わずかな不備が、製品の安全性や品質に直結するため、工場内では日々細かな衛生管理が欠かせません。
しかし、食品工場を実際に見学してみると一見整理整頓され、きれいに保たれているように見える現場でも、実は食品の安全を脅かすリスクが潜んでいることに気づかされます。
本記事では、食品工場で潜む衛生リスクの具体例を紹介するとともに、現場で役立つ改善のヒントや、さらに詳しく学べるセミナーの情報をご案内します。
食品工場でよく見られる衛生リスク
食品工場内でよく見られる衛生リスクには、次のようなものがあります。
- 排水処理槽のメンテナンスが不十分で、菌の繁殖源となっている
- 製品や原料が床に近い位置に置かれ、二次汚染のリスクが高まっている
- 常に濡れている床が菌の温床となり、さらに従業員の転倒リスクを引き起こす
- 手洗い場が乱雑で、衛生的に使えない状態になっている
- 外部と内部の着替え場所が同じで、外部から菌が工場内に持ち込まれてしまう
- 使用されている建材の防汚性や防水性が低く、清掃がしづらい構造になっている
こうしたリスクは、日常の作業に慣れてしまうと見過ごされがちです。
「ハード」と「ソフト」を両立させる衛生管理
食品工場の衛生管理を考えるうえで重要なのは、「ハード」と「ソフト」の両立です。
- ハード:建物や設備などの物理的な側面
- ソフト:日々の運用や衛生的な作業手順
例えば、以下のような改善が効果的です。
- 原料や製品を床から60cm以上の高さに置くルールを徹底する(ソフト)
- ホースを床に接触させない構造にする(ハード)
- 給水管を縦管化して清掃しやすくする(ハード)
- 次亜水での定期的な洗浄を行う(ソフト)
これらは大規模な投資をしなくても取り入れられる工夫です。設備の改善(ハード)と、作業手順の改善(ソフト)を組み合わせることで、より確実なリスク低減につながります。
既存工場の改修では「床を新しくすれば解決する」「新しい機械を導入すれば安心できる」と考えがちですが、それだけでは十分ではありません。改修後も運用方法がそのままではリスクが残り、期待した効果が得られないケースもあります。だからこそ、施設改善と運用改善を一体で考える視点が求められるのです。
見落とされがちな「菌の存在」
衛生管理において、意外と見落とされがちなのが「食品作業環境には常に菌が存在する」ということです。
肉眼では清潔に見える場所でも、思いがけないところに菌が潜んでいる可能性があります。
どのような菌が、どの場所に潜み、どのようなリスクをもたらすのかを把握することは、工場運営に携わる方々にとって欠かせません。
菌の存在を正しく理解することで、衛生管理への意識が高まり日々の運用改善にもつながります。
食品工場の衛生対策を徹底解説!建設会社 × 微生物検査会社によるセミナー
ここまで紹介してきた課題や改善のポイントを、より具体的に学べるセミナーを9/30(火)に開催します。
当日は、菌検査・衛生管理を専門とする食品微生物検査支援会社である日本細菌検査株式会社の髙橋様と、食品工場建設を数多く手掛けてきたSAWAMURAのJHTC HACCP上級コーディネーター鈴木が、それぞれの知見から衛生的な工場運営を行うために必要なポイントを解説します。
食品工場の新設や改修を検討している方はもちろん、日々の衛生管理に悩みを抱える方も、この機会にぜひご参加ください。
お申し込みはこちら
- 執筆者
-

-
JHTC HACCP上級コーディネーター / MBA
- 鈴木 戒
2020年からSAWAMURAの食品工場プロジェクトに参画。2022年から正式入社し同職に。食品工場建築と資産活用で多くの実績を持つプロフェッショナル。
-
- コピーしました
- この記事を印刷する
- メールで記事をシェア






.jpg?width=704&height=396&name=%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%81%A6%E3%81%AE%E9%A3%9F%E5%93%81%E5%B7%A5%E5%A0%B4%E5%BB%BA%E8%A8%AD%E3%80%82%20HACCP%E3%81%A8%E8%A1%9B%E7%94%9F%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%9C%AC%20(1).jpg)
















