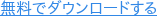事故やトラブルを防ぐ、工場の安全対策とは?

-
一級建築士 / 一級建築施工管理技士
- 宮前 聡志
- コピーしました
- この記事を印刷する
- メールで記事をシェア

どんな事業であろうと、安全衛生対策には真摯に取り組む必要があります。それは働く人を危険から守るだけでなく、業務効率や生産性の向上につながり、工場全体にとってプラスをもたらします。ここでは工場で取り組むべき安全対策について統計を交えながら解説します。
工場で起こり得る事故やトラブル
労働災害は「転倒」が一番多い
厚生労働省が令和3年にまとめた労働災害統計では、全産業通じての死傷災害発生状況は多い順に「転倒」12.5%、「墜落・転落」7.4%、「動作の反動・無理な動作」7.3%、「はさまれ・巻き込まれ」2.0%と続きます。「その他」53.6%がもっとも多く、発生状況は多岐にわたることがわかります。
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/toukei_index.html
ヒヤリ・ハットから甚大な事故まで
労働災害事例を見ると、例えばフォークリフトが「転倒」して運転者が下敷きとなった死亡災害から、棚から箱を下ろそうとしてつまずき「転倒」しそうになったヒヤリ・ハット事例まで、「転倒」だけ挙げても、さまざまな事例が見られます。
原因は無数に挙げられる
発生要因は「物・人・管理」に分類され、例えば「物」に起因する場合は物自体や安全装置、作業環境や方法の欠陥などが挙げられ、「人」に起因する場合は心理的・生理的・職場的原因が挙げられています。「管理」には安全対策を怠った要因などが挙げられています。
事故やトラブルを未然に防ぐには
5S活動で作業環境を整える
まずは働きやすい安全な環境を整備する必要があります。そのために5S活動が有効です。5Sとは、Sを頭文字にもつ「整理・整頓・清掃・清潔・しつけ」の5つの言葉を意味します。
まず「整理・整頓」することで必要なものだけを選別し、置き場所を決めて使いやすくします。そして「清掃」して「清潔」にすることでその状態を維持し、誰もがいつでも作業のしやすい環境を整えます。さらに全員がそれらを「しつけ」として身につけ、習慣化させます。
KY活動で危険を予知する
KYは「危険」を「予知」することを意味します。仕事を始める前に、危険な箇所を確認し、作業する人全員で共有します。行動目標を周知したり、指差し呼称をすることも事故の抑止につながります。
働く人の健康に配慮する
働く人にとって働きやすい環境を5S活動で維持しつつ、より良い社風をKY活動で培ったうえで、しっかり休息することも、また大切なことです。人の注意力には限界があり、人はミスをすることを前提に考えておくべきです。健康診断やメンタルヘルス対策など、健康管理を行うことも必要です。
機器のメンテナンスを行う
人のミスに比べると、機械が故障する確率は格段に低いといいます。しかし、ひとたび事故が起これば、その力の大きさから致命的な結果につながりやすいのも事実です。工場で使用する機器が正しく動作するか、定期的な点検やメンテナンスを行う必要があります。
さらにできること
ムリ・ムラ・ムダを洗い出す
トヨタ自動車の豊田英二氏は「安全な作業は、作業の入り口である」と基本理念に掲げ、「安全な作業」とは「ムリ・ムラ・ムダのない作業」だと定めました。事故は定められたルールどおりに作業が行われないところから生じています。ルールから外れるのは、そこに不具合があるからです。
工場や倉庫ができてから年月が経過している場合、新しく追加した機械によって施設内の動線などが変化し、作業効率が下がっている可能性もあります。それらを見極め、ムリ・ムラ・ムダを洗い出す必要があります。
従業員からの改善提案を聞き取る
労働安全衛生法では、50人以上が働く事業場では安全委員会などを設置することが定められています。その規模に該当しなくても、工場で働く人たちから意見を聞き取ることは重要です。あらゆる現場で働く人が感じているムリ・ムラ・ムダなことを聞き出して、改善へとつなげましょう。
安全装置などの設備に投資する
機器が動作する範囲に安全柵やカバーを取り付けたり、巻き込まれ防止のためのセンサー、落下防止のためのストッパーを設けるなど、あらかじめ安全対策を講じておくことも必要です。さらにインターロックの仕組みを設けたり、パワースーツや機械化を取り入れて作業者の負荷を減らすことも視野に入れます。
最近ではWELL認証など、働く人の健康を重視したオフィスの評価制度も注目されているので、オフィスリニューアルなどを通じて、働きやすいオフィスを再構築することも有効な手段のひとつです。
WELL認証について詳しく知りたい方は「WELL認証とは?基本情報やメリット、評価項目について解説」の記事もご覧ください。
まとめ
事故やトラブルの要因はひとつではなく、いくつかが重なって起こります。発生要因をひとつでもなくすことが事故やトラブルの防止につながります。しかし固有リスクは減らせても、残留リスクはゼロにはなりません。人的ミスや機械の故障を補うためにも、安全対策を日頃から講じていくことが大切です。
安全対策以外にも考えなければならないポイントはいくつかあります。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
- 執筆者
-

-
一級建築士 / 一級建築施工管理技士
- 宮前 聡志
営業企画課課長。工場管理経験と設計業務を経験し、2018年にSAWAMURAに建設プロデューサーとして入社。現場・設計・営業を知るオールラウンダー。
-
- コピーしました
- この記事を印刷する
- メールで記事をシェア