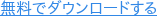【2025年4月施行】建築基準法改正で工場はどう変わる?影響ポイントを解説

-
GRAPHISOFT認定BIMマネージャー / BSI Professional Basic
- 徳永 康治
- コピーしました
- この記事を印刷する
- メールで記事をシェア

2025年4月、建築基準法が大きく変わりました。今回の改正は、カーボンニュートラルや省エネ義務化といった社会的な流れを背景に「工場や倉庫などの産業用建築」にも直接影響を与える内容です。
本記事では、工場を持つ企業が知っておくべき主な改正ポイントとその影響、そして今後の対応方法について解説します。
建築基準法とは?
建築基準法は、日本全国の建築物に適用される法律であり、安全性や環境性能を確保するために定められています。工場をはじめとする事業用の建築物もこの法律の対象であり、定期的な改正によって最新の技術や安全基準が反映されます。
2025年4月に施行された今回の改正は「2050年カーボンニュートラルの実現」や「2030年度温室効果ガス46%削減(2013年度比)」を目指し、産業施設の設計・建設基準を強化するものです。 工場や倉庫などの建設に関わるルールも変更されるため、影響を受ける企業は事前に準備を進める必要があります。
今回の改正が工場建設にどのような影響を与えるのか、主な変更点を紹介します。
改正の主なポイント
4号特例の縮小
これまでは、規模が一定以下の建築物には建築確認申請の一部手続きが免除される「4号特例」が適用されていました。しかし、改正後はこの特例の適用範囲が縮小され、以下の建築物でも審査が必要となります。
- 木造2階建て
- 木造平屋建てかつ延床面積200㎡以上
4号特例の適用範囲が狭まることで、工場建設においてもこれまで以上に厳密な審査が求められる可能性があります。例えば、木造の小規模事務所等を工場敷地内に建設する場合などがあります。コストも安く工期も短い木造ですが、申請料や申請期間が比較的長くなります。
木造建築物の規制緩和
中大規模の木造建築が、より建てやすくなりました。
これまでも木造で中大規模の建物を建てることは可能でしたが、工法や設計に大きな制約がありました。今回の改正により建築可能な工法の選択肢が広がり、より自由な設計が可能になります。ただし、木造であっても耐火性能や耐震性など、一定の技術基準を満たす必要があるため、設計段階での慎重な検討が欠かせません。
例えば、以下のようなタイプの工場で木造建築が現実的な選択肢となります。
- 火器を使用しない工場
- 大スペースではなく比較的省スペースをたくさん要する工場(小型精密部品組み立て工場・畜産建屋など)
- 農業用倉庫・加工工場
- 木質空間が企業イメージにつながる工場
- 家具・建材工場、農業関連工場
省エネ基準の義務化
2025年4月以降に着工するすべての建物において省エネ基準への適合が義務化されます。増改築を行う場合にも省エネ基準が適用されるため、工場の改修計画にも影響を与えます。
省エネ対策は法令順守だけでなく、工場の長期的な運用コストの削減にもつながります。
例えば、省エネ対策として以下のような対策があります。
外壁に断熱素材を使用する
工場の外壁や屋根といった外皮部分に断熱素材を使用することで、内部の温熱環境が大きく改善されます。構造がシンプルで外皮の面積が広い工場は断熱性能の向上による効果が特に大きく、高いコストパフォーマンスが期待できます。
再生可能エネルギーを活用する
工場は平面的に大きな屋根面積を確保しやすく、太陽光発電などの再生可能エネルギーと非常に相性が良い建物です。さらに、太陽光パネルは日射を吸収するため、屋根面からの熱の侵入を抑える効果もあります。
LED照明を使用する
現在、国内メーカー製の照明器具の多くはLEDが主流になっています。LED照明は従来の照明に比べて消費電力が少なく、長寿命であるため、省エネに大きく貢献します。
工場建設・改修を検討している企業が今やるべきこと
現在の工場が法改正の影響を受けるか確認する
自社工場の現状が以下のような場合、特に注意が必要です。
- 小規模な建築物の増改築を計画している
- 木造建築を検討している
- 省エネ基準に適合していない設備を使用している
専門家へ相談する
建築基準法の改正内容を正確に理解し自社の状況に応じた対策を講じるためには、専門家との連携が不可欠です。
- 建築士や施工業者に相談し、法改正対応の具体策を検討する
- コストや工期への影響を事前に把握する
- 補助金の活用の有無を検討する
まとめ
建築の法制度は複雑で、計画の規模や用途によって必要な対応も変わってきます。だからこそ早めに専門家に相談して、方向性をクリアにしておくことが大切です。
SAWAMURAでは、工場建設に精通した専門家が、最新の法律に沿った設計・施工をご提案しています。「今の計画はこのままで大丈夫?」「新ルールに合わせるにはどうすればいい?」このようなお悩みがある方はぜひご相談ください。
- 執筆者
-

-
GRAPHISOFT認定BIMマネージャー / BSI Professional Basic
- 徳永 康治
主任設計者。2019年からBIM導入を先導、BIMマネージャーとして各地で講演を行っている。JIA建築年鑑100選受賞歴有。
-
- コピーしました
- この記事を印刷する
- メールで記事をシェア