工場見学開催のすすめ

-
中小企業診断士
- 和田山 翔一
- コピーしました
- この記事を印刷する
- メールで記事をシェア
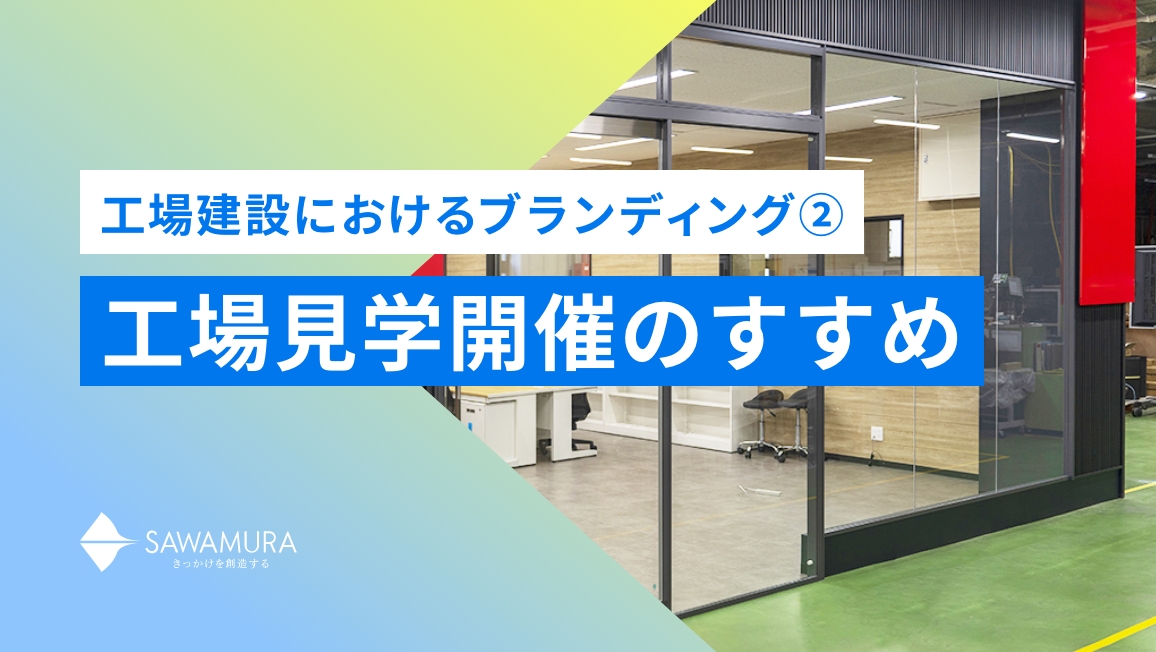
ものづくり産業の集積地を中心に、地域が一体となって生産現場を外部に公開する取り組みが全国各地で行われています。また企業単体でも魅力ある工場見学が実施され、人気を集めています。経営層だけでなく社員が能動的に取り組む工場見学がブランディングに有効であることを、事例を交えて紹介します。
地域一帯で工場をひらく取り組み
「燕三条 工場(こうば)の祭典」は、鍛冶や金属加工の産地として知られる新潟県の燕市と三条市の工場を一斉に開放し、ものづくりの現場を見学・体験するイベントです。
2012年からはじまり、毎月10月に行われる4日間のイベントは、参加工場も来場者も年を追うごとに増え、コロナ禍前は113の工場に5万人超の人が訪れ、2024年には108の工場に3万8000人超が来場しました。
普段は閉ざされている工場を訪れた人は、そこで働く人と触れ合い、その技術を間近に見たり、体験型のワークショップに参加したり、大人も子どももものづくりの魅力を知ることができます。
「FactriSM(ファクトリズム)」は、大阪府の八尾市・東大阪市・門真市・堺市の町工場を開放し、ものづくりの現場を体験するイベントです。2020年12月の4日間の開催からはじまりました。
こうしたイベントを経済産業省近畿経済産業局では「地域一体型オープンファクトリー」とし、さまざまな事例をまとめています。
企業単体でも工場をひらこう
企業単体で行う、いわゆる「工場見学」の受け入れは全国各地で実施されています。自分たちの生産現場を公開することで社員の意識を高め、ファンを集め、新規受注を獲得し、人材採用につなげる企業もあります。
参考事例|企業単体で取り組むオープンファクトリー集(近畿経済産業局)
多くのメリットがある一方で、安全面や衛生面、知財やノウハウ流出などには注意が必要です。工場見学時の禁止事項を掲示したり、立ち入りや撮影を制限したうえで工場見学ルートを設定するなど、工夫は必要です。
まずは家族にひらこう
こうしたメリットとデメリットを踏まえたうえで、まずは家族や身内に向けて工場を開くことをおすすめします。
協和精工(長野県高森町)では毎年1回「家族の参観日」を設定し、社員の家族に向けて工場を開放しています。
人を迎えるために工場を整え、危険箇所を洗い出し、トイレや休憩室を見直すことは、働きやすさへの改善につながります。また、自分たちの働く現場を見てもらい、訪れる人に自分の仕事を説明することで、仕事への自負にもなります。
また家族同士が顔を合わせることで社員の親睦が深まり、工場が働く場であるだけでなく、楽しく人が集う場になったといいます。
次に社会にひらこう
期日を決めて工場を開放したり、子どもの社会見学を受け入れることで、地域住民に企業の取り組みを知ってもらい、子どもには大人が働く現場を体感してもらいます。
地域住民にとっては自分たちの住むまちの魅力を再認識するきっかけとなり、企業にとっては、これまでにない地域社会との接点を持つことで、企業としての誇りの醸成や新たなビジネスの契機になります。また学生向けの工場見学は採用にもつながります。
見られる意識が社員に浸透すると、職人たちの技術やモチベーションが向上したり、子どもたちに伝わるように説明することが社員自身の理解力を深めたり、安全・衛生管理への配慮にも結びついています。
さらに地域の観光ガイドで「工場」から「観光地」として扱われるようになり、単体の工場見学が地域一体型オープンファクトリーとして産業観光につながるきっかけとなった工場もあります。
工場見学をブランディングにつなげた事例
工場見学という取り組みは、企業のブランディング活動そのものです。企業の価値を社員と共有するインナーブランディングから、社会と共有するアウターブランディングに発展した事例をいくつかご紹介します。
石田屋(福井県永平寺町)|日本酒蔵の複合施設を設け、建物を自然に調和するよう設計・デザインすることでアーティスト、デザイナーなど多様な人が集まるクリエイティブな場となり、新しい価値を創造する呼び水になった。
坂田織物(福岡県八女郡広川町)|久留米絣のプロダクトを紹介するギャラリーを設置し、ものづくりの現場を積極的に開放して見てもらう環境を整備することで、新たな収益源の確保や、これまで縁のなかった世代の取り込みに成功した。
安田蒲鉾(福井県福井市)|工場見学の開始当初は製造に集中したいと考える社員から反対の声もあったが、粘り強く取り組みを続けるうちに手伝ってくれる社員が増え、現在は社員が積極的に携わるようになった。小学校の見学受け入れは地域産業の啓発、食育の推進に大きな役割を果たしている。
京屋染物店(岩手県一関市)|来場者の反応から自分たちの価値に気づき、さらに深掘りすることで新たな価値の提供につながった。地域の古民家を改築して里山体験施設を開設し、セレクトショップ、ギャラリー、カフェ、手仕事体験や里山整備など、地域に根ざした新しい体験を提供している。
湯浅醤油(和歌山県湯浅町)|古式製法での醬油づくりの蔵を見学できる順路を整え、醬油発祥地として文化発信と後継育成の取り組みにも力を入れている。蔵見学を通して職人を目指す学生の採用や大手メーカーとのコラボ、海外との取引などにつながっている。
SAWAMURAは、地域の製造業をデザインの力で変える工場建設に取り組んでいます。デザインの力でブランディングを推進する工場建設に興味がある方は、SAWAMURAまでお問い合わせください。
- 執筆者
-

-
中小企業診断士
- 和田山 翔一
SAWAMURAのブランディングを担い、社内外におけるコミュニケーションをデザイン。ワークショップ・ファシリテーションのスキルを活かした顧客提案も手掛ける。
-
- コピーしました
- この記事を印刷する
- メールで記事をシェア




















