【セミナーレポート】はじめての食品工場建設セミナー~HACCP工場ってなに?~

-
JHTC HACCP上級コーディネーター / MBA
- 鈴木 戒
- コピーしました
- この記事を印刷する
- メールで記事をシェア
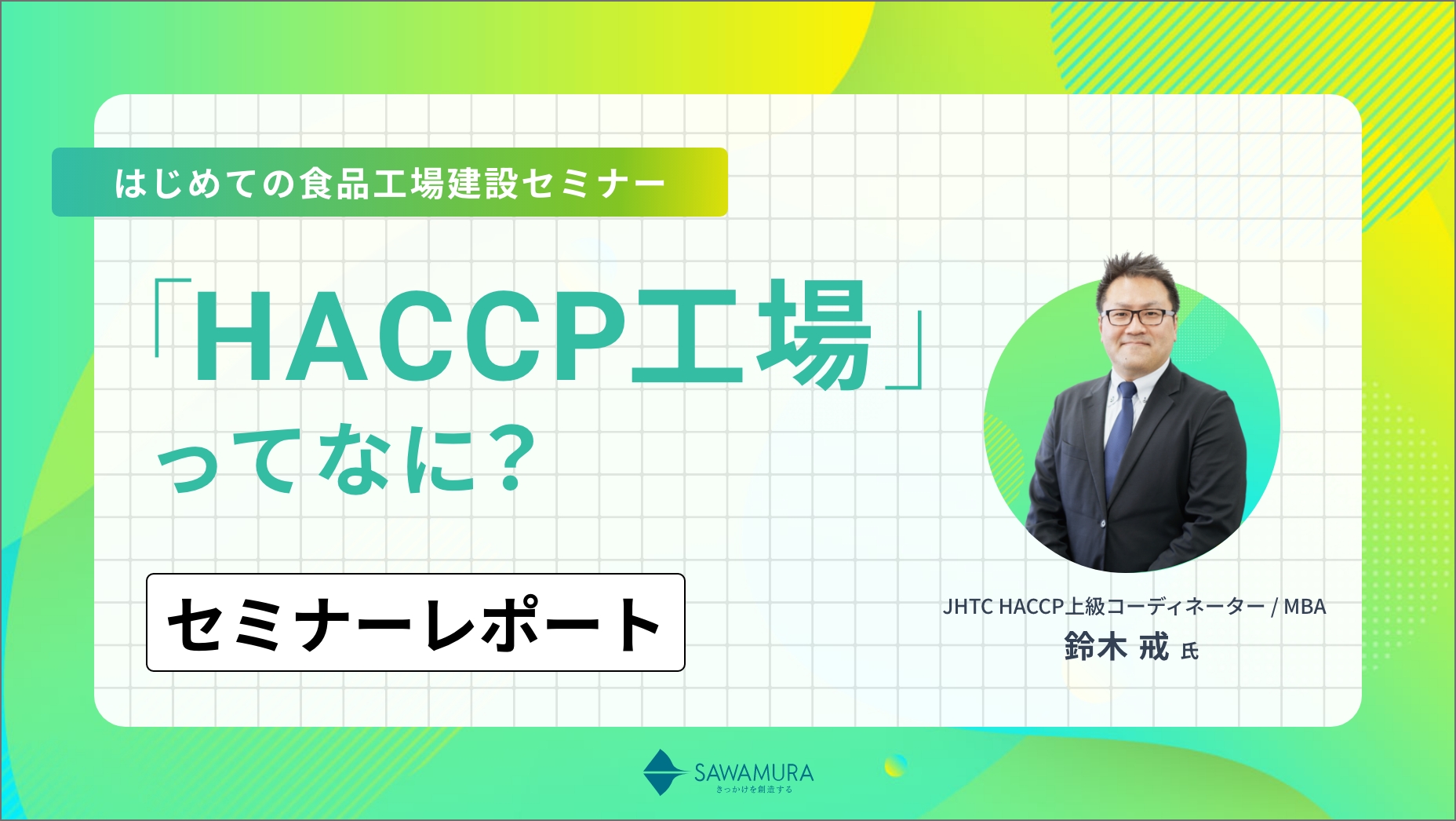
『はじめての食品工場建設セミナー 第1回「HACCP工場ってなに?」』は、初めて食品工場建設に携わる事業者を対象にしたセミナーシリーズの第1回として開催されました。
講師は、食品工場建設の現場で多くの課題解決を支援してきた、株式会社澤村の食品工場コンサルタント・鈴木さん。制度化以降、対応が求められるHACCPの基本から、「HACCP対応工場」をつくるうえで欠かせない施設設計の視点まで、実践的な内容が紹介されました。
本レポートでは、HACCPの基本から「HACCP対応工場」の施設設計におけるポイントまで、食品事業者が押さえるべき観点を整理しています。これから食品工場の新設を検討されている方はぜひご覧ください。
HACCPとは
HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)とは、食品の製造過程において、食中毒や異物混入などの危害要因を事前に特定し、リスクの高い工程を継続的に管理する手法です。令和3年6月に制度化されました。
HACCPは「品質管理」ではなく、「安全性の確保」に焦点を当てた仕組みです。対象となる危害要因は以下の通りです。
- 生物的危害要因:細菌、ウイルス、寄生虫など
- 化学的危害要因:アレルゲン、カビ毒、農薬や薬剤の残留など
- 物理的危害要因:金属片、ガラス、プラスチックなど
また、HACCPはあくまで管理手法であり、「HACCPそのもの」に規格や認証制度があるわけではありません。そのため、「HACCP認証」というものが存在するわけではなく、HACCPの考え方に基づいて構築された食品安全マネジメントシステムに対して認証が付与される仕組みです。
「HACCP対応工場」とは「HACCPの管理がしやすい建物」
「HACCP対応工場」や「HACCP工場」という表現はよく使われますが、HACCP自体に施設の基準や規格があるわけではありません。俗にいう「HACCP対応工場」とは、HACCPの仕組みを円滑に運用するために必要な土台(一般衛生管理、GMP、SSOP、SOP、5Sなど)が施設設計において十分に考慮されている建物を指します。

これより、建設会社の視点から「HACCP対応工場」に求められる情報や理解について具体的に紹介します。
HACCPの基盤となる施設設計と運用
HACCPの仕組みを効果的に運用するには、日々の作業や衛生管理の基盤となる情報を、施設の設計段階から取り入れておくことが不可欠です。特に「5S」や「SOP/SSOP」といった日常業務の要素が、建物や動線の構成に大きく関わります。
5Sの視点から考える設計の工夫
5S(整理・整頓・清掃・清潔・習慣)は、食品工場における衛生管理の基本です。これらが施設設計とどう結びつくのか、以下に代表例を紹介します。
- 整理:要るものと要らないものを区別し、不要なものを処分すること。施設計画では残渣(ざんさ)の置き場やゴミ処理の方法に紐づきます。
- 整頓:必要なものを必要な時に必要な量を取り出せるように所定の場所に保管すること。物の定位置管理がしやすいように、包装材や梱包材が取りやすい位置に保管します。
- 清掃:ゴミや汚れ、埃を除去し、常に使える状態に保つこと。食品関連では「洗浄」「消毒」も加わり、施設や器具の洗浄・消毒方法に応じた部材の選定に紐づきます。
- 清潔:整理、整頓、清掃により施設を清潔な状態に保つこと。施設計画ではゴミや埃が付着・滞留しない部材の選定に繋がります。
- 習慣:整理、整頓、清掃についてルールを設け、教育訓練し、施設の清潔が常に維持されるように習慣化すること。施設計画では分かりやすい動線設計や視覚的なエリア区分に紐づきます。
SOP・SSOPの視点から必要な情報を読み取る
現場の作業手順や衛生管理の方法を設計に反映するには、標準作業手順(SOP)や衛生標準作業手順(SSOP)の理解が欠かせません。
- SOPの把握:作業動線の確認、交差汚染を防ぐゾーニング設計に役立ちます。
- 機器・器具情報:洗浄スペースの確保や建築コストの最適化に寄与します。
- SSOPの確認:ウェット/ドライエリアの分離、調湿・換気計画、衛生区域の設定に直結します。
実例から学ぶGMPに基づく施設・衛生管理の工夫
GMPに関わる具体的な事例を交えながら、施設設計に必要な視点を紹介します。
- 敷地管理:山や川が近い場合、虫や野生動物の侵入リスクが高まるため、剪定や除草、定期的な清掃、側溝の詰まり確認などが必要です。
- 建物構造:排水溝に目皿や残渣カゴがないことで起こる詰まりや臭気、天井のカビ発生などのリスクがあります。

床と壁の継ぎ目を丸くする「R構造」や、機器の下にスペースを確保することで清掃性が向上します。

- ドライ化:床に水が残ると大腸菌群が検出されやすくなるため、乾燥を促す排水設計や床勾配の工夫が必要です。

- 衛生設備:手洗い・更衣室・ロッカーなどの動線は衛生リスクの低減に直結します。非接触型設備の導入や作業着脱スペースの確保も重要です。
- 器具管理:ウェット環境では器具を床から30cm以上、可能であれば60cm以上離して保管することが推奨されます。

- 交差汚染防止:食品の安全性を確保するためには、原材料(容器包装資材を含む)、仕掛品、手直し品、再生品、最終製品などの間で汚染や交差汚染が起きないよう、あらかじめルールを定めておく必要があります。
あらゆるリスク要因を想定し、ゾーニングや動線分離、作業時間の調整などの対策をSOPやフローダイアグラム(工程図)に基づいて具体化していくことが求められます。
まとめ:HACCPに対応する工場は、設計(ハード)と運用(ソフト)の両面から考える
HACCPに対応した食品工場をつくるためには、施設の設計(ハード)と、日々の運用(ソフト)の両面から計画を進めることが不可欠です。その実現には、以下の取り組みが重要です。
- 食品事業者からの詳細な業務内容・衛生ルールの共有
運用ルールや製造フローを正しく理解しない限り、設計に落とし込むことはできません。 - 現場の作業フローや管理手順を設計に反映
動線設計やゾーニング、機器配置などは、現場の運用に即して計画する必要があります。 - 計画初期からの運用と設計のすり合わせ
施設の使い勝手や清掃性、メンテナンスのしやすさなどは、初期段階から考慮することで後戻りのない設計が可能になります。
これらを実現するためには、食品業界の実務と衛生管理に理解があり、設計に反映できる建設パートナーの存在が極めて重要です。
実際の現場で求められる機能やルールを正確に把握し、それを設計に反映できることは、長期的な衛生運用やコストの最適化につながります。
セミナー動画をご覧いただけます
当日のセミナーは動画でもご視聴いただけます。以下のフォームよりダウンロードしてご覧ください。
動画ダウンロードフォーム
- 執筆者
-

-
JHTC HACCP上級コーディネーター / MBA
- 鈴木 戒
2020年からSAWAMURAの食品工場プロジェクトに参画。2022年から正式入社し同職に。食品工場建築と資産活用で多くの実績を持つプロフェッショナル。
-
- コピーしました
- この記事を印刷する
- メールで記事をシェア











